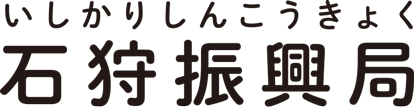北海道の家畜保健衛生所では、獣医系大学の大学生、大学院生の研修を実施しています。
北海道には、全国で最も多い家畜保健衛生所(14カ所)があり、約180名(定員)の職員(獣医師)が地域の家畜衛生の拠点として活躍しています。
研修では、現場で働く獣医師が、日頃の業務・仕事の内容を紹介しています。家畜の疾病診断のための検査を体験したり、職員の生の声を聞いたりすることができます。
産業動物に関わる仕事、公務員、家畜保健衛生所の仕事に興味のある方は是非体験してみましょう!!
1.インターンシップとは
◆インターンシップって、どういうことをするの?
インターンシップとは、学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行うことです。多くの場合、受け入れ側では、効率良く仕事の内容がわかるような、インターンシップ用の研修メニューを用意しており、職場で実際に行っている様々な仕事を体験したり、多くの職員と話をすることができます。
◆インターンシップのメリットは?
○仕事や職場の状況を深く知ることができます。
実際の仕事内容に近い体験をしたり、職員から話を聞いたりすることで、業種や職種による仕事内容の違い、やりがい、会社の風土(雰囲気)、待遇などの違いを体感することができます。
○専門知識の重要性が理解でき、学習意欲に対する刺激を得られます。
希望する職場で必要とするスキルがわかります。大学での学習が「就職後に役に立つ」という実感がわきます。ややもするとマンネリ化する学生生活で、目標ができ、学習意欲が高まります。
○仕事や自分の適性や能力について考える機会となり、就職後、職場への適応力を高めることができます。
職場の説明資料などによる知識と実際の仕事には少なからずギャップがあります。事前に仕事を体験することで、自分がこの職場に向いているか、などを考えるきっかけとなり、就職してから「こんなはずではなかった」というようなミスマッチを防ぐこともできます。
○就職活動に生かすことができます。
職員の生の声を聞いたり、仕事を体験することで、面接の際に、より具体的に志望動機を語れるようになるなど、就職活動に生かせる利点があります。
2.北海道の家畜保健衛生所で実施するインターンシップについて
◆主な内容は、「講義:家畜保健衛生所の業務と役割」、「講義・実習:監視伝染病の検査、診断、防疫」などで、職員に同行し「畜産現場」へ行くこともあります。
◆研修時期:8月~9月頃
1 北海道庁インターンシップ
募集期間:例年5月
2 行政体験研修
産業動物臨床実習・行政体験研修(臨床実習等支援事業)(公益社団法人 中央畜産会)
(研修に必要な交通費、宿泊費の一部が助成されます)
募集期間:例年5月~6月
※8月~9月以外でも受け入れが可能な場合があります。北海道庁(下記)へお問い合わせください。
◆申し込み先
○各獣医系大学に募集の案内をお送りしています。(例年4月)
○参加申し込みは、各学部の先生、事務担当部署等にお尋ねください。
○大学では各募集期間より早く締め切られますので、早めに行動してください。
○大学での受け付けが終了した場合などは、北海道庁(下記)、中央畜産会へ直接お問い合わせください。
◆問い合わせ先
○家畜保健衛生所でのインターンシップ、採用試験に関するお問い合せは・・・
北海道庁 農政部 生産振興局 畜産振興課 家畜衛生係
電話:011-204-5441
◆オンライン個別相談窓口もあります。 常時受け付けていますのでお気軽にご連絡ください。インターンシップや採用試験の他、様々なお問い合わせに対応します。社会人の方でもOKです。
3.家畜保健衛生所の組織と業務・採用試験
◆家畜保健衛生所は都道府県の機関です。
○家畜保健衛生所に就職するためには、地方公務員採用試験を受検します。
○北海道の場合は、獣医師専用の選考試験となります。
○採用試験については、こちらをご覧ください。
○子育て支援制度が充実しており、子育てしながら働ける職場です。
○社会人の方の再就職にも対応しています。
○オンライン個別相談窓口
◆北海道職員としての獣医師(選考職)の職場は・・・
(1)農政部 : 家畜保健衛生所、生産振興局(道庁)
(2)保健福祉部 : 食肉衛生検査所、保健所、健康安全局(道庁)
(3)環境生活部 : (総合)振興局保健環境部環境生活課、観光局(道庁)
※北海道の場合、(1)と(2)(3)の人事交流は原則ありません。
◆北海道の家畜保健衛生所
○14カ所あり、約180名(定員)(うち70名程度が女性)が働いています。
○そのうち、4カ所が病性鑑定課を備えた中核家保です。
○家畜保健衛生所内は、指導課、予防課、病性鑑定課、BSE検査室に分かれています。(規模等によって構成は異なります)
◆家畜保健衛生所の役割と業務
家畜保健衛生所は、疾病による家畜の損耗防止と畜産物の安全性確保を推進することにより、畜産の振興を担っています。
日本では、海外から急性・悪性伝染病の侵入が見られており、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの大規模な発生により、畜産を始め地域経済に大きな損失を与えた事例も発生しました。国内においても、生産性を阻害する様々な疾病が存在します。
また、食中毒(腸管出血性大腸菌やサルモネラなど)や牛海綿状脳症(BSE)など、家畜や畜産物を介して人の生命や健康に影響を与える疾病が発生し、消費者の「食の安全性」に対する関心は一層高まっています。
家畜保健衛生所は、生産現場に最も近い立場にあり、家畜衛生分野におけるエキスパートとして、高度な知識と技術の提供により、生産者や関係者の指導機関として、北海道の酪農・畜産の抱える課題解決のため積極的に取り組んでいます。
○ 動画で紹介!家保の職場の実態や働き方 (日本獣医師会のHP)
※リンク先の「公務員(行政)分野」
平成31年度に、北海道の家畜保健衛生所業務紹介が掲載されています。
○ 職員からのメッセージ
採用後に実際にどのような働き方をしているか、また、やりがいを感じることなど、先輩職員の生の声をお届けします。
○ 日本における家畜衛生の概況 (農林水産省HP)
※リンク先の「2-1 最近の家畜衛生をめぐる情勢について」をご覧ください。
○ 石狩管内の紹介